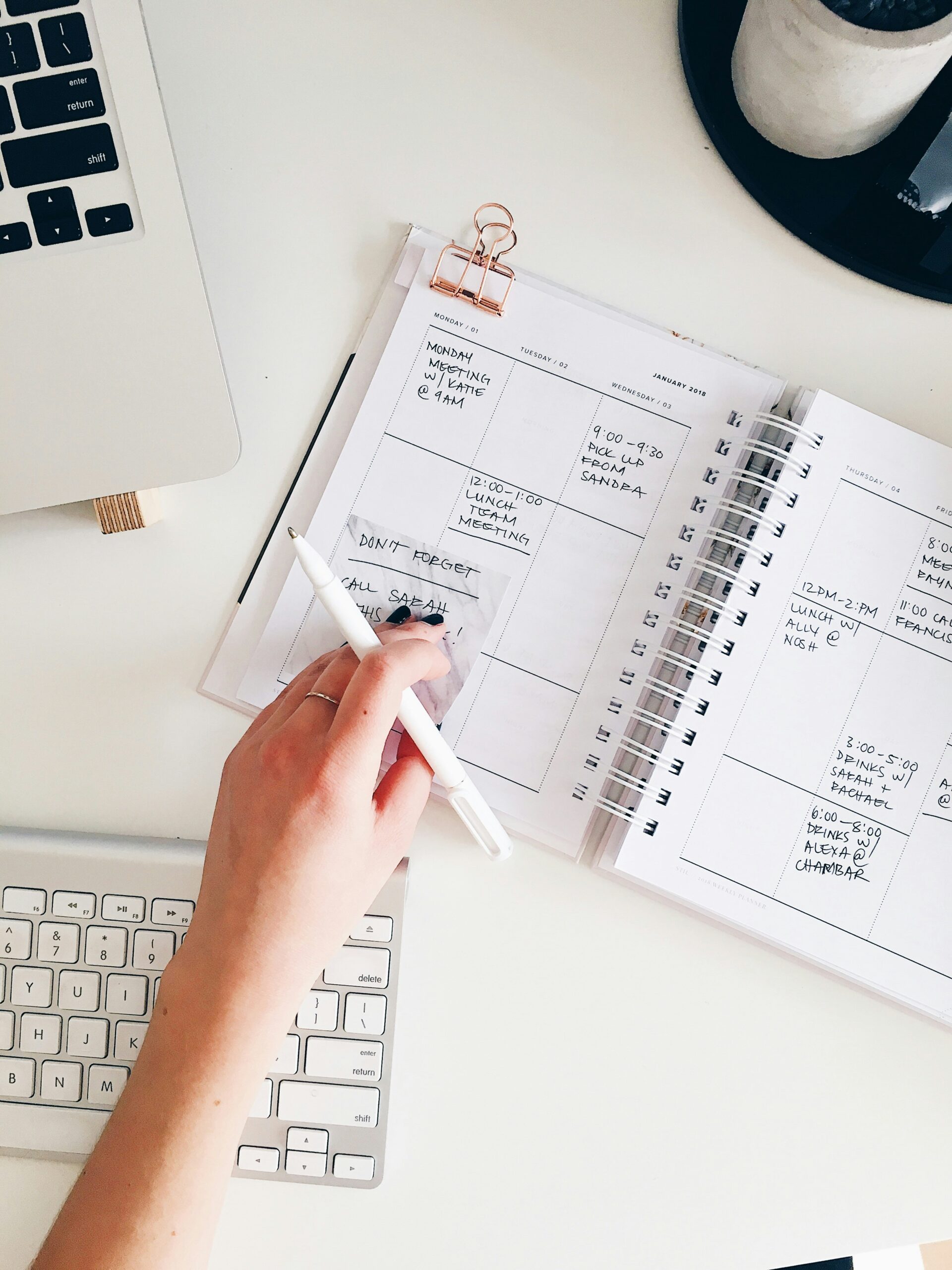勝率を高めるための現実的プランニング
医療機器営業において、目標達成のためには「数字の現実性」を見極めることが不可欠です。今回は、目標金額に対して今いくら足りないのか、そしてそれを埋めるために毎月どれだけ新規を積み上げる必要があるのかを、丁寧に分析する方法をご紹介いたします。
はじめに:現実的な数字を把握する重要性
目標に対して現実的な数字を把握していなければ、仮に100%プランを実行できたとしても未達に終わる可能性があります。そのため、数字の分析にはじっくりと時間をかけ、念入りに計算することが求められます。
方法:逆残法を推奨します
「逆残法」とは、与えられた目標数値から現在の積み上げ額を計算し、不足分を明確にする方法です。以下に具体的な手順を示します。
① 過去1年間の数字の流れを把握する
- 過去1年間の新規案件、失注案件を洗い出します。
- 今日から期末まで何もしなかった場合の今期の着地金額を算出します。
- 消耗品の場合、前期に獲得した案件や失った案件の金額が今期に継続して影響します。
- 箱物の場合、前期に進めていた予算申請が今期の採用に影響します。
- 新規ビジネスを除き、既存ビジネスでは前年からの数字が基盤となるため、ここはしっかりと把握しておく必要があります。
② 毎月のノルマを算出する
- 目標額と今期の予測金額の差を算出します。
- その差額を月数で割ったものが月間ノルマとなります。
絶対のルール:リスクを洗い出し、最悪のシナリオを想定する
ノルマを算出する際に絶対不可欠なルールがあります。それは、
「起こりえる現実味のあるリスクをすべて洗い出し、それらがすべて現実になったときのシナリオを作成しておくこと」
です。
営業はロングランであり、予想外の出来事が毎年のように起こります。1年で結果を出さなければならない環境にあるため、予想外の事態に備えたリカバリー策が必要です。したがって、プランニングの基本は「何が起きても達成できる数字をあらかじめ追っておくこと」であり、これが「負けないプランニング」となります。
リスクの事例
以下に、現実的に起こりうるリスクの事例を挙げます。
- 前任者も気づいていない失注案件の存在 引継ぎが行われたとしても、それは前任者の知っている範囲内の話です。実際には知らないところで競合がシェアを広げていることがあります。担当変更後に失注案件に出会い、そのままマイナスを引き継ぐケースも多くあります。損失があれば、その額が今期にどの程度響くかをシビアに見積もる必要があります。
- 医師の移動、診療科の撤退、自主回収など 毎年4月、6月には医師の定例異動が行われます。ヘビーユーザーが異動すると使用量が減少し、売上が自然と下がります。診療科全体の撤退も稀にあります。既存数字が大きいビジネスでは基盤が崩れ、新規営業どころではなくなります。また、自社側の自主回収や欠品なども頻繁に起こります。これらが原因で失注した場合、営業が責任を負うことが多く、準備はしすぎることはありません。
- 売り上げ予想が外れる 製品が採用されたとしても、それがゴールではありません。予測よりも売り上げが少ないケースも存在します。予測売り上げの精度は採用後に判明するものであり、予定を下回ると挽回は困難になります。採用された時点でようやくスタートラインに立ったという認識が重要です。
まとめ:期初の計画がすべてを決める
まともに計画を立てられるのは期初の1回だけです。ここでリスクを考慮していないと、現実離れしたプランニングになります。期中の下方修正は、始まって間もなければぎりぎり可能ですが、後半に差し掛かると修正は困難です。
したがって、初めから最悪を想定した条件のもとで計画を立てることが、最も勝率の高い方法となります。
また、Excelなどを活用してエリア内の数字をすべて可視化することを強くお勧めいたします。エリア担当者であれば、売上の構成要因をすべて把握しておく必要があります。数字で怖いのは「不意なへこみ」であり、それを防ぐためにも「見えない数字の存在」はゼロにしておくべきです。
追記:前任者問題について
耳の痛い話を一つ。既存ビジネスでは前任者からの引継ぎが行われることがほとんどですが、前任者のやる気次第で大きく外れることがあります。
次の赴任先でも真面目に取り組む担当者であれば、誠実に引継ぎしてもらえますが、他部署への異動や退職などで足取りが途切れる場合は、まず逃げられます(法令上、引継ぎの義務はありません)。また、コンプライアンス上、都合の悪い案件は隠されることもあります。
とにかく、情報を引き出せる時期は「今しかない」ので、上司の力や会社の力を使ってでも、すべてを引き出すべきです。スタートラインがまったく変わってきます。
おすすめの方法としては、最低限教えてほしい内容をまとめた「質問シート」を作成しておくことです。相手に主導権を持たせると漏れが多くなるため、それを回避する手段として有効です。
ご自身の営業活動において、数字分析とリスク管理は「勝てる営業」の土台となります。ぜひこの内容を参考に、現実的かつ堅実なプランニングを実践してみてください。
【数字分析の理解を深めるならこの1冊】
「会社では教えてもらえない 数字を上げる人の営業・セールストークのキホン」
Amazonはここから https://amzn.to/3KZt1MD